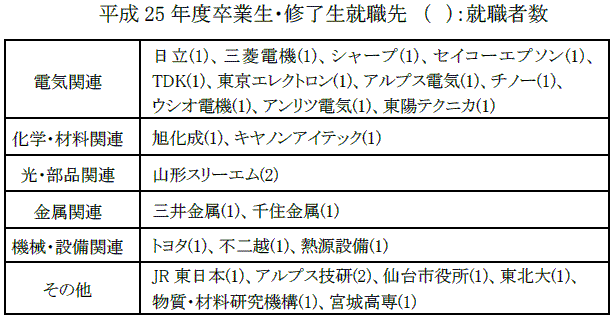

久々の就職担当。教育・研究以外の我々の役割を再認識するいい機会でした。学生にしてみれば大学はこれがためにあるようなもので、在学中で最も重要な活動(の一つ?)といっていいでしょう。また、私たち教員にとっても会社との数少ない接点の一つであり、社会の動向を知る上でも重要な役目であります。
昨年1月24日に就職ガイダンスを開催し、スケジュールや現況の説明、希望調書の配布、そして卒業生との懇談会を行いました。今回お願いした卒業生は、磯村明宏氏(東北大学産学連携推進本部、14期生)、久保田均氏(産総研、23期生)、工藤成史先生(応物、10期生)、川股隆行先生(応物、32期生)です。それぞれ、卒業後の経験を通して感じ取った「応物で学ぶことの意義」を熱く語っていただきました。学生に希望調書を2月25日まで提出してもらい、3月中に推薦の調整や会社への確認の連絡等を行いました。今年度推薦依頼があった会社は約120社で、前年度と同等です。4月1日から推薦書類の送付を開始し、順次面接試験等に臨みました。
結果からみますと、表に示すように、最終的な就職先は(例年通り)電気関係が多いのですが、第一希望としては材料メーカーや部品メーカが多かったのが今回の大きな特徴です。これは、半導体産業の低迷に伴い、大手電機メーカーが軽薄短小から重厚長大へ大きく舵を切り、主力製品を半導体からインフラやシステム設計に移行しつつあるのを学生が敏感に感じ取ったためと思われます。結果として国内の多くの学生が材料メーカーに集中したことで、元々採用数の少ない材料メーカーの倍率が上がり、応物の学生は紆余曲折の末に電機メーカーに落ち着いた、というのが実際のところでしょう。
結局、H25年度も学生側の売り手市場というわけにはいかなかったのですが、人生の幸・不幸が入った組織で決まるものではなく、ましてや入口のところで決まるものでないことは、目下就活中の学生も大学入学以降を振り返ってみれば、容易に察しが付くでしょう。私が日ごろ身近な学生に「会社はサイコロで決めろ」と言っているのはこのためです。特に、変化の周期が短い最近の企業は、内定をもらったときと入社の時点で事情が変わっていることがあります。株はピークのときに買ったらもう遅いので、そのときの人気と勢いに流されないようにすることが肝要です。安定な経営が保証されている会社など存在しないわけですから、逆境こそ好機と捉えて、自分の真の力を発揮できるようなタフな人材を会社は求めているわけです。会社をサイコロで決めるのはまずいですが、現時点での優良企業を見極める力より、逆境力を養いしなやかに生きるすべを身に着ける方が大切ではないでしょうか。面接試験に正解はありませんが、これまで経験してきた(多くの?)挫折をどのように克服してきたかをアピールするのも一つの手かもしれません。就活のみなさん、がんばってください。
